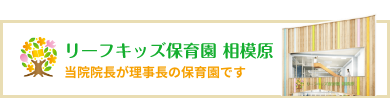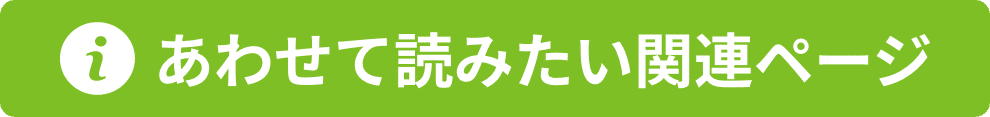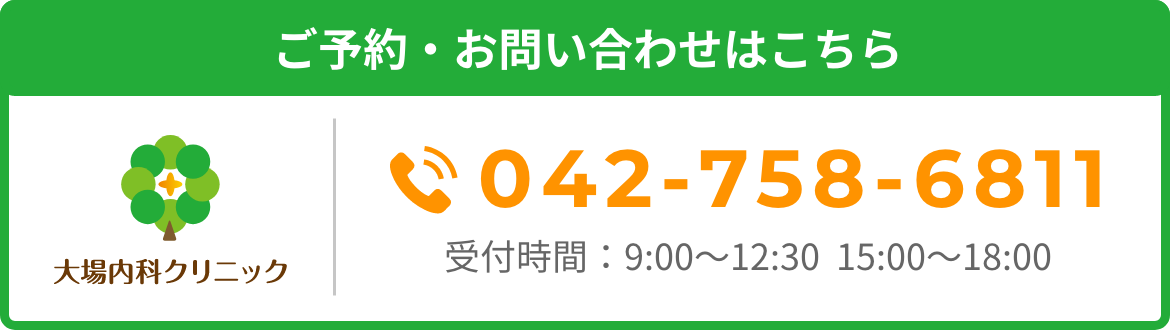2025.07.04(Fri) - 10:47 - 10:47 am
色神検査(色覚検査)を含む健康診断
色神検査(色覚検査)を含む健康診断
健康診断の項目に『色神(しきしん)』が含まれていませんか?
赤、緑、青のいずれかの色が見えづらい状態を『色神異常』といいます。
ほとんどの『色神異常』が生まれつきで、男性が多いとされています。
『色神検査』は石原式というちょっと特殊な色覚検査を行います。痛くも痒くもありません。カラフルな絵を何枚か見て頂くだけです。
色神検査(色覚検査)は通常の健康診断項目ではないので、オプションになり、¥1,100(税込)かかります(色神検査(色覚検査)のみでは受付ておりません)。
JR相模原駅1分
色神検査(色覚検査)を含む健康診断
健康診断の項目一覧を見ていて、「色神って何?」と思ったことはありませんか?普段あまり聞き慣れない言葉なので、「これって必要なの?」「どんな検査をするの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
実際に当院でも「色神検査って書いてあるんですけど、これは何ですか?」というお問い合わせをよくいただきます。今日はこの色神検査について、その歴史から現在の状況まで、わかりやすくご説明していきますね。
「色神検査」という名前の由来と歴史
健康診断の項目に「色神(しきしん)」が含まれていませんか?この「色神検査」という名称、実は古い歴史を持つ言葉なんです。
「色神検査」という名称は、かつて日本で色覚検査を指す言葉として使われていました。「色神(しきしん)」とは、色を感じ取る能力や色覚そのものを指す古い表現で、明治から大正時代にかけて使われていた歴史的な用語なんです。
実際に、明治から大正時代にかけて、徴兵検査や学校検診などで色覚異常の有無を調べる検査が導入され、その際に「色神検査」という名称が用いられました。1910年には日本初の色覚検査表として「色神検査表」が作成され、1916年には石原忍博士による「石原式色神検査表(現在の石原式色覚異常検査表)」が徴兵検査用に開発されたんです。
色覚異常とは?基本的な知識
現在では「色神検査」という言葉は「色覚検査」と呼ばれるのが一般的です。色覚異常とは、色を感じる視細胞の異常によって、正常とは違った色の感じ方をしている状態のことを指します。
赤、緑、青のいずれかの色が見えづらい状態を「色神異常」といいます。ただし、最近では「色覚異常」や「色覚特性」という表現が使われることが多くなっています。これは、色の見え方が違うことを「異常」と捉えるのではなく、一つの「特性」として理解しようという考え方が広まってきたからです。
ほとんどの色覚特性が生まれつきで、男性に多いとされています。その多くを占める「先天赤緑色覚異常」は、日本人男性の約5%(20人に1人)、日本人女性の約0.2%(500人に1人)の割合で見られると言われています。思っているより身近な特性なんですね。
色覚異常の種類と特徴
色覚異常には、主に3つのタイプがあります。1型色覚異常(プロタン)は赤の感受性が低下するタイプ、2型色覚異常(デュータン)は緑の感受性が低下するタイプ、3型色覚異常(トリタン)は青の感受性が低下するタイプです。
全ての色は、赤・緑・青の3つの光の組み合わせによって構成されており、色を感じ取る視細胞にもそれぞれに反応するものがあります。色覚異常はこれらの視細胞に不足があったり、うまく機能しなかったりといったことが原因で起こります。
色覚異常の強さには個人差がありますが、多くの場合は日常生活で困ることはありません。検査を受けて指摘されない限りは気付かないことも多いです。
石原式色覚検査の方法と特徴
「色神検査」は石原式というちょっと特殊な色覚検査を行います。痛くも痒くもありません。カラフルな絵を何枚か見て頂くだけです。
この石原式色覚検査は、日本の眼科医である石原忍博士が開発した世界的に有名な検査方法なんです。明度や彩度が異なる多数の丸模様を無作為に配置した検査表を用いたスクリーニング検査で、図の中にある文字や形を被検者に読み上げてもらい、誤読数で色覚異常の有無を調べます。
「学校の健康診断で見たことがある!」という方も多いのではないでしょうか。検査時間は5分程度で、特別な準備も必要ありません。眼鏡をかけている方は、眼鏡をかけたまま検査を受けていただきます。色覚検査表には、色覚に異常がある方にとって見分けにくい組み合わせの数字と背景が使用されているため、色覚が正常な方には容易に判別できる図も、色覚に異常があると判別できなかったり、反対に色覚に異常がある場合には濃淡が強調されて判別されたりします。
より詳細な検査方法
色覚検査には、スクリーニング検査と詳細検査の2つのタイプがあります。一般的には、まず色覚検査表を用いたスクリーニング検査から行います。色覚異常が疑われる場合は、程度判定を目的に色相配列検査やランタン・テスト、アノマロスコープなどの詳細検査を行います。
アノマロスコープ検査は、色覚検査の中で唯一確定診断が可能とされる検査です。被検者に特定の光を提示して簡単な等色法(色合わせ)を行い、色覚異常の型や程度を判定します。検査は、赤色と緑色の混ざり合った光と黄色の光を比較して、2つの光が同じに見えるところを探します。その時の赤色と緑色の混合比や光の強さ、同じ色に見える範囲などから色覚異常の型や程度を判定します。
学校での色覚検査の変遷
色覚検査の歴史には、複雑な変遷があります。2002年までは小学校4年生全員に対して色覚検査が実施されていましたが、「差別につながる」という理由で、2002年に学校保健安全法施行規則の一部が改正され、健康診断の必須項目から除外されました。
これは80年にわたって行われてきた一律色覚検査の廃止となりました。しかし、平成26年4月30日、学校保健安全法施行規則の一部改正に伴う局長通知が出され、健康診断の実施に関わる留意事項として色覚検診に関する指導強化の内容が示されました。現在は、保護者に対し先天色覚異常と検査の周知を図り、希望者に検査を行うことが推進されています。
以前は入学を制限していた大学や専門学校もありましたが、近年ではほとんど見られなくなりました。とはいえ、色覚特性が原因で希望の職種に就けないといったこともあり得るため、自分の色覚特性を知らずに進学して、就職活動をする時になって色覚異常があるため希望の職種に就けないと分かった場合、そこから進路を変更するには大変な労力が必要です。
どんな時に色神検査が必要になるの?
色神検査(色覚検査)は通常の健康診断項目ではないので、オプションになることが多いです。では、どんな時に必要になるのでしょうか?
まず、就職時の健康診断で求められることがあります。特に、電気関係の仕事、交通関係の仕事、医療関係の仕事などでは、安全上の理由から色覚検査が必要とされることがあります。また、運転免許の取得時にも、場合によっては詳しい色覚検査が必要になることもあります。
学校関係では、教員採用試験や一部の専門学校の入学時に求められることもあります。ただし、最近では色覚による職業制限は大幅に緩和されており、多くの職種で色覚特性があっても問題なく働けるようになっています。
セルフチェックの注意点
近年は、スマホやパソコンを使ってセルフチェックできる、オンラインサイトやアプリも増えてきました。しかし、一般的な色覚検査では検査距離が決まっています。また、色覚検査表は印刷物を使って色の判定をすることが前提ですので、スマホやパソコンのディスプレイに表示させるオンラインやアプリでの検査結果には、信憑性が欠ける可能性もあります。
セルフチェックでの判定結果は正確性に欠けるため、あくまでも参考程度と考えてください。正しい色覚検査を受けるためには、眼科や内科クリニックを受診して相談しましょう。
当院での色神検査について
JR相模原駅から徒歩1分の当院では、色神検査(色覚検査)を実施しています。検査費用は1,100円(税込)となっており、他の健康診断項目と一緒にお受けいただけます(色神検査のみでの受診はお受けしておりません)。
「色覚検査の結果について詳しく聞きたい」「色覚特性があると言われたけど、どういう意味?」「仕事への影響が心配」など、どんなご質問でもお気軽にお聞きください。
色覚特性は決して恥ずかしいことでも、隠すべきことでもありません。多くの著名人やアーティストの中にも色覚特性を持つ方がいらっしゃいますし、その特性を活かして活躍されている方もたくさんいます。色覚異常には残念ながら治療はありませんが、先天色覚異常は自分で自分の異常に気づきにくく、家族や先生、友人に指摘されて「自分の見え方は周りと違う」ことに気づくことが多いです。
大切なのは、自分の特性を正しく理解し、必要に応じて適切な対応を取ることです。検査結果についてご不明な点があれば、いつでもご相談ください。一緒に最適な対応方法を考えていきましょう。